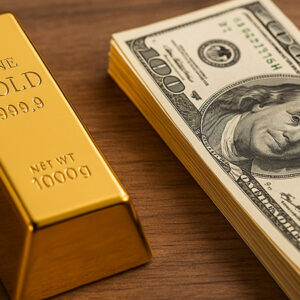シチズンの歴史とは?創業からの技術革新〜世界進出まで徹底解説
最終更新日:2025/08/20


大嶋 雄介
2010年にゴールドプラザに入社し、千葉店の店長として3年間で月間売上の最高記録を達成。鑑定士としてのキャリアをしっかりと積み上げました。その後、集客の戦略構想やSNSを活用したPR活動をしながら、リサイクル業界への深い理解と経験を積みました。現在は貴金属の換金業務に従事し、金融相場や市場動向の分析を通して緻密な専門知識を深化させています。BSテレ東「なないろ日和」や日本テレビ「ニュースゼロ」などに出演。
◾️ 目次
日本を代表する腕時計ブランド「シチズン(CITIZEN)」。その名は世界中で知られ、信頼と革新の象徴として高い評価を受けています。しかし、現在のグローバルブランドに成長するまでには、多くの挑戦と革新的な技術開発がありました。
本記事では、シチズンの創業から技術革新、国際展開、そして近年の動向までを徹底解説します。
シチズン(CITIZEN)とは?ブランドの誕生と初期の歩み
尚工舎時計研究所の設立と「CITIZEN」の誕生
シチズンの歴史は、1918年(大正7年)の「尚工舎時計研究所」の設立に始まります。当時、日本では高品質な時計製造技術が未熟で、輸入時計が主流でした。そんな中、時計金属商・山﨑龜吉が「国産懐中時計を作りたい」という夢を掲げ、研究所を立ち上げます。
1924年には、初の懐中時計に「CITIZEN(市民に親しまれる時計)」と名付けられ、これが後にブランド名として定着しました。1930年には「シチズン時計株式会社」が正式に設立され、国産時計メーカーとして本格的に歩みを進めます。
戦前・戦中から戦後へ ― 信頼の基盤づくり
シチズンの懐中時計は高精度で、昭和天皇が愛用したとも言われています。戦中には計器類や軍需製品も製造しましたが、戦後は大衆向け製品の普及に注力。1956年には日本初の耐衝撃機構「パラショック」を搭載した腕時計を発売し、「丈夫で信頼できる時計」という評価を確立していきました。
国産技術の進化と挑戦 ― 世界初の数々
光発電時計「エコ・ドライブ」の誕生
1976年、世界初のアナログ式太陽電池時計「クリストロン ソーラーセル」を発表。これが、シチズンの代名詞ともいえる「エコ・ドライブ」の原点です。「エコ・ドライブ」は、太陽光や室内光で駆動し、電池交換不要という環境にやさしい技術で国際的評価を獲得しました。
世界を驚かせた技術革新
- 1978年:世界初、ムーブメントの厚さ1mm未満の超薄型クオーツ「エクシードゴールド」発表
- 1993年:世界初、光発電+電波受信機能を備えたアナログ式クオーツ時計を発売
こうした「薄型・軽量・高精度・環境配慮」の技術革新は、シチズンをグローバルブランドへと押し上げました。

世界進出とグループ戦略
グローバル市場での評価
1990年代以降、シチズンは北米・欧州・アジア市場へ積極展開。特に「エコ・ドライブ」や「アテッサ」はビジネスパーソンやミリタリーファンから高く評価されました。
ブランド拡大の取り組み
- 2008年:アメリカの老舗時計ブランド「ブローバ(BULOVA)」を買収
- 2016年:スイス高級機械式ブランド「フレデリック・コンスタント」を傘下に
これにより、クオーツから機械式・スマートウォッチまで幅広いラインナップを展開し、グループ全体の競争力を高めています。
近年の動向とシチズンの未来
サステナブルな時計づくり
近年は、環境配慮と先進技術の両立をテーマにした製品開発が進んでいます。
- 「エコ・ドライブ ワン」:極薄デザインと光発電機構を両立
- リサイクルチタンやバイオマス素材の採用
スマートウォッチ市場への展開
GPS衛星時刻補正やスマホ連携を搭載したモデルで、次世代のユーザー層にも支持を拡大しています。
まとめ:シチズンの歴史が示すもの
シチズンの歩みは、国産時計の発展そのものです。
「市民に親しまれる時計」を理念に掲げ、創業以来100年以上にわたり技術革新を続けてきました。
近年では「アテッサ」「プロマスター」「ザ・シチズン」などの高級ラインが再評価され、コレクション市場でも注目を集めています。
ご自宅に眠るシチズンの時計も、思わぬ価値があるかもしれません。歴史と技術に裏打ちされたシチズンは、今後も世界中で愛され続けることでしょう。